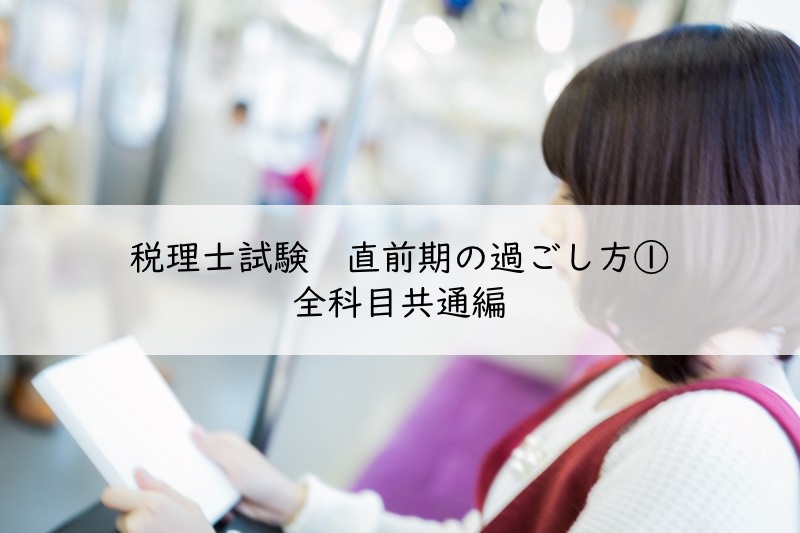8chunmama
8chunmamaはじめまして。8chunmama(はっちゅんママ)です。
税理士受験対策の各学校では、直前期に入りました。
各科目、改正事項も織り交ぜながらの総復習と、試験形式の問題を解く練習をする時期です。
この時期の過ごし方で、
「もう一歩」のところからグンと点数が伸びる人
と、
ずっと上位だったのに本試験で実力を発揮できない人
との明暗が分かれる、とも言われる、大切な時期です。
フォロー体制がある指導校では「よくある質問」にも色々アップされることもある話題ですが、
本試験経験者の私が考える、まずは全科目共通の「直前期の過ごし方」についてご紹介します。
「試験が終わったらやりたいこと」リストを作る
これは色々な講師の方がアドバイスしていることでもあります。
してはダメな時期ほど、やりたいことは出てきます。
でも、試験が終わると燃え尽き症候群となり、残暑に負けている間に、次の勉強が始まって
しまうことも。
スケジュール帳でも、専用メモ帳でも、スマホのメモ機能でも、なんでもいいです。
思いついたときに、サッとメモして、モチベーションを上げていってください。
部屋の片付け、帰省や旅行、美容院・散髪、読書、
久々のリアル飲み会。
今は我慢していることを書き出してください。
全国模試は通過点として捉える
官報合格済の人ほど言うのが、
全国模試で点数を取りに行くな、
ということです。
私が参加している勉強会メンバーの税理士さんは、現役生への直前期のアドバイスを求められると
誰かが必ずこれを言い、皆さん頷いています。
全国模試で出た論点は、受験者が皆復習するので、模試が終わってからの復習は必要です。
出題者が「捨て問」として出した論点ならともかく、理解できないまま本試験を迎えるのは危険です。
でも、あなたが目指すのは、模試のS判定・A判定ではありません。その約1.5~2ヶ月先にある
本試験の合格です。ピークは本試験に持っていく、それまでは力を蓄える時期です。
模試で出そうな論点をヤマかけしに行くのではなく、直前期の3ヶ月を通した計画を立てて、自分のペースでこなしていってください。
また、模試でB判定が出ても本試験に合格する人もいますし、S判定・A判定でも本試験は残念な結果になることもあります。
模試の結果に一喜一憂することなく、その先を目指しましょう。
できることなら、生活リズムは朝型にシフトを
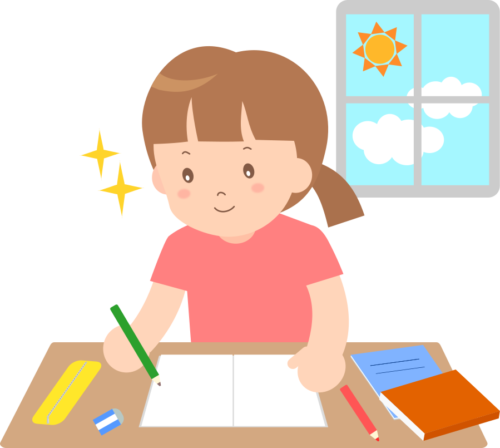
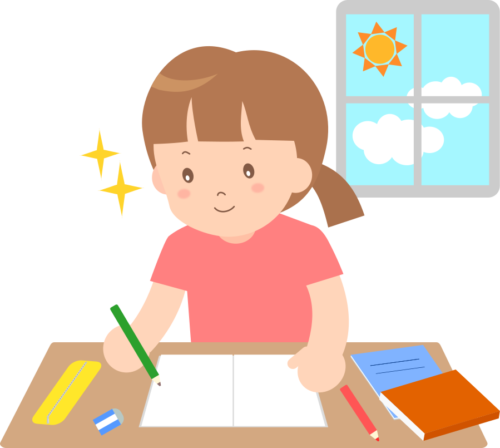
夜型人間の私が言うのも何なのですが。
学生の頃から含めた経験則から言うと、夜早く寝て朝に勉強できる人は、成績がいいです。
それくらい、自分をコントロールできる人だから、というのもあるでしょう。
人間が睡眠中に脳内の記憶を整理している、というのもあると思います。
私は朝起きるのが苦手です。もし朝予定より早く起きて二度寝しなかったとしても布団の中で考え事を1時間くらいできてしまう人間なので、夜早く寝てしまって次の日の朝早く起きられる保証なんてない、と思って、夜に活動してしまうタイプです。
でも、暗記物や計算は夜に疲れた脳で何時間もするべきではありません。
いくら忘却曲線の傾きが睡眠を挟むと傾きが緩やかになるとしても、クリアでない頭で何時間分も頑張った暗記がそのまま定着したことは、私はありません。
朝早く起きて日光を浴びるとセロトニンという神経伝達物質が分泌され、精神的にもポジティブになれます。
通勤・通学されている方は、計算問題を解く分の時間だけ普段より早く起きて、60分や80分など自分で決めた時間で総合問題を解き、通勤電車で解説を読んだり、お昼休みに答え合わせをするのもいいでしょう。
前日に解いた問題の間違った箇所のリトライをする復習タイムにするのも、定着させるのには最適です。
夜型の私が、独身時代、本試験のほんとに直前の時期だけですが、早起きして、簿記論の総合問題を1問解いてから出勤する、というリズムにしたことがありました。
官報合格した知人で、朝、カフェで勉強してから出勤していたという人もいます。
簿記論・法人税法・国税徴収法という、本試験の時間割でその日の1科目めにある科目を受験する場合は、尚更、朝型の生活をオススメします。
何時に起きて、何時にご飯を食べれば、何時に頭がシャキッとするか。
平日が難しいのであれば、休日に色々なパターンをシミュレーションして、ベストな組み合わせを探されるとよいと思います。
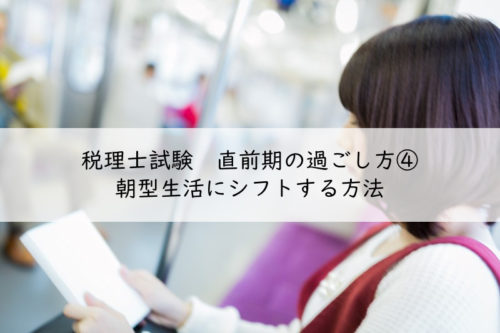
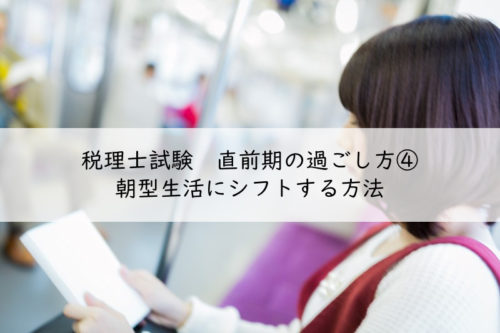
色々な新しい教材に手を出さない
これは大学受験を含めたどんな受験でも色々な人が主張しています。
その科目が2年目・3年目だとか、受験専念型で1科目のみ受験とかなら、いいかもしれません。
でも、とりあえず、手元にある教材をやりこんでください。
新しい教材を手に入れて、やり残して、手を付けていないところから出るんじゃないか、と不安になる方が精神衛生上よくありません。
去年はTが当たった、Oが当たった、等々はあるでしょう。
同じ受験指導校のオプション市販教材に手を出すかどうか、も悩むところではあります。
しかし、私としては、やることをやりつくした2年目以上の受験経験者にのみ、オプションの問題集をお薦めします。
すべての教材の内容を知りたくなるのが人情ですが、なぜそこまでしなくてもよいのか、といいますと・・・。
すべての受験生が理解しておくべき論点を全く取りこぼさず、半分くらいの受験生が理解していることをあまり失点しなければ、その積み重ねで合格点に達する、というのが実際だからです。
重箱の隅をつついたような問題や、たまたま1つの指導校のみが取り扱っていた論点が出題されても、そこは合否に影響しない、というのが講師の先生の話です。試験委員は、各指導校の教材を取り寄せ、どこかだけが取り上げていた論点は避ける、というのです。確かに、試験の公平性だけでなく、癒着を疑われないようにするためにも、試験委員がそうしていてもおかしくないなと思いました。
特に計算問題の場合でニッチな論点は、時間をかけて勉強したり解答したりするべきではありません。費用対効果を考えた方が良いです。
大手と言われる指導校であれば特に、手元の教材を信じて、やりこんでください。
授業料がリーズナブルな、対面授業の無い指導校には、ごめんなさい、私のデータがありません。でも、合格実績が相当数ある指導校のものなら、教材をやりこんでみて、これじゃ物足りないと思えるような理解度になってから、他社教材に手を出してみてはいかがでしょうか?
私の場合、自分が勉強している以外の受験指導校の教材については、授業はT社一筋、国税徴収法の理論教材のみ2年目で購入しました。
理論を覚えたのはT社の理論教材を使ってでしたが、O社の教材にはT社にない理論が数個あって、それも覚えたいと思う余裕が出来たのと、O社はT社とは別の理論のまとめ方をしていた、という理由があったからです。O社は条文番号のくくりではなく、理論の解答の柱になりそうな組み合わせでまとめていたのが魅力でした。
また、私の国税徴収法の受験2年目の直前期は、自分の子どもが4月に幼稚園へ入園し、短いながらも確実に勉強時間を確保できるようになったという状況でもありました。時間的にも、科目のボリューム的にも、他社教材を見てみる余裕があったからこその「もう1冊」でした。